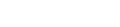UNIQLO Co. Ltd.
UNIQLO Co. Ltd.
12/19/2025 | News release | Distributed by Public on 12/20/2025 19:07
映画、難民に出会う。 難民映画基金 映画監督ハサン・カッタンさんインタビュー
映画、難民に出会う。 難民映画基金 映画監督ハサン・カッタンさんインタビュー
Dec 19, 2025 NEWS
ユニクロは、難民や避難を経験した映画制作者、または避難民としての経験を描いた実績のある映画制作者の作品制作を支援する「難民映画基金(Displacement Film Fund)」をサポートしています。創設パートナーとして、ユニクロは10万ユーロを寄付し、彼らの物語にスポットライトをあて、難民や避難民への理解を深める活動を後押ししていきます。
難民映画基金による第一回の支援を受けることになった5名のうちの1人、シリア出身の映画監督ハサン・カッタンさんは故国のシリア内戦をどのように撮りつづけたのでしょうか。
戦火のもとでつくられたドキュメンタリー映画の現場と、ロンドンで制作中の次作について、お話をうかがいました。
映画監督になるまでの歩みについてお聞かせください。
1992年、シリア北部の都市アレッポに生まれました。ごく普通の家庭で育ちました。子どもの頃は平和な日々で、日本のアニメの「名探偵コナン」や「ポケットモンスター」、「ドラゴンボール」や「ONE PIECE」などを夢中になって見ていました。大学に進んでからは法律を学びました。その頃、自由と民主主義を求める人々の声がシリア国内でおおきくなり、アレッポでも平和的なデモが始まりました。私もその運動に触発され、デモに参加しました。
▲ アレッポ、2016年12月 - 包囲された東アレッポからの家族たちが、6か月に及ぶ包囲の後に締結された避難合意に基づき、ラモーセ交差点で待機している様子。数千の家族が、過酷な人道状況の中、何時間も地面に座って「緑のバス」や赤新月社およびICRC(国際赤十字)の車列による市外への避難を待っていた。ⒸAMC(Hasan Kattan - Aleppo Media Center)
デモが拡大し、2011年にシリアでの蜂起が始まったとき、私はスマートフォン1つで、目にしたものを撮影し始めたのです。何が起きているのかを記録し、外の世界へ伝える義務を感じたからです。市民ジャーナリストやメディア関係者の仲間が集まって設立した、「アレッポ・メディア・センター」の共同設立者の1人になりました。戦争犯罪や軍隊に包囲された都市での日々の現実を記録し、報道することが、自分の仕事になっていったのです。私たちにとって、ここでの物語を伝えることは単に生きていくためではなく、抵抗そのものでした。
▲ 『We Will Return My Love』 アレッポ、2016年12月 - 包囲下で結婚し、その後故郷を離れざるを得なかったカップルのラブストーリーを描いた短編映画の主人公、サーレハとマルワ。写真は、爆撃と包囲の後、避難のための「緑のバス」が到着するのを待っている間に撮影されたもの。ⒸAMC(Saleh Hasnawi - Aleppo Media Center)
報道の仕事からドキュメンタリー映画の制作へと向かったのはなぜでしょうか。
私はニュース編集者や記者という役割で、BBCやChannel 4、アルジャジーラ・イングリッシュ、その他の国際NGOとも仕事を重ねてきました。報道の仕事をつづけるのが何より大切でした。
アサド政権とそれを支援する同盟者が、プロパガンダや偽情報をさかんに流すことによって、人々のほんとうの物語が歪められ、消し去られる可能性があったからです。こうした偽りの情報に騙されず、真実を守り、保存して、伝えていくという報道の使命を信じて、十年あまり活動してきたのです。
▲ ハナーノの民間防衛センター(アレッポ、2016年) - 映画『アレッポ 最後の男たち』の撮影中に撮影された写真。ホワイト・ヘルメットのボランティアが空を見上げ、住宅街に樽爆弾を投下しようとしているヘリコプターを追跡している様子が写されている。この瞬間を、ハサンさん(写真左)は脅威を感じながら観察・報告しながら記録していた。ⒸAMC(Thaer ِAlHalabi - Aleppo Media Center)
最初のうちは、映画作家になるつもりはありませんでした。ただ、圧倒的な困難や不正義、目の前で起きている、語られないままの人間の物語に接するうちに、自分がいま目撃し、見聞きしているものを、もっと深く取材し、撮影して、広く伝えていかなければならないと思うようになりました。ここにいない人をも動かすような物語になりうるのは、ドキュメンタリー映画ではないか、と気づいたのです。
大きな話題となり、さまざまな賞を受けることになったドキュメンタリー映画『ホワイト・ヘルメット』(2016年 アカデミー賞短編ドキュメンタリー映画賞受賞)について話を聞かせてください。どのような立場でこの映画に関わりましたか?
『ホワイト・ヘルメット』の撮影は、私にとって職業的にも個人的にも、大きな転機となりました。私はアレッポ・メディア・センターのチームの一員として、シリア国内で撮影監督を務めました。「ホワイト・ヘルメット」の隊員は、アレッポの街で爆撃を受けた現場に駆けつけ、最も危険な瞬間に、瓦礫の下に生き埋めになった人々を救い出すボランティアとして活動する、ごく普通の人々です。彼らはしばしば、次につづく爆撃の脅威にさらされていました。
この活動を記録することは、何よりも危険で感情を揺さぶられる状況の彼らとともに活動をするということと同義でした。私たちは彼らとともに救急車に乗り、爆撃現場に入り、捜索救助の痛ましくも果敢な瞬間を捉えました。彼らが救助した人々は、多くの場合、すでに命を落としていました。しかし、そのような喪失の瞬間においても、彼らの人間性、勇気、そしてどんな犠牲を払っても他者を救おうとする信念を目の当たりにすることは、計り知れない力となりました。
私たちの使命は、彼らの日々の生活を誠実に記録し、何が起こっているのかという真実を伝えることでした。彼らに寄り添うことで、私は変わりました。それはただ事実を写し取るのではなく、彼らの声と犠牲を世界に伝えることでした。
『アレッポ 最後の男たち』(2017年 アカデミー賞長編ドキュメンタリー部門ノミネート作品。サンダンス映画祭ワールド・シネマドキュメンタリー・コンペティション部門グランプリなど世界中で23の映画賞を受賞)には、どのように関わられましたか?
▲ 『アレッポ 最後の男たち 2017』 監督:フェラス・ファヤード 共同監督:スティン・ヨハネセン 第90回アカデミー賞長編ドキュメンタリー部門ノミネート作品。2017年サンダンス映画祭ワールド・シネマ ドキュメンタリー・コンペティション部門グランプリ。ほか、世界中で23の映画賞を受賞した。配給:ユナイテッドピープル/©Larm Film
『アレッポ 最後の男たち』では、私はディレクターチームの一員で、撮影監督も務めました。2年以上にわたり、アレッポのホワイト・ヘルメットの隊員たちと活動をともにしました。撮影では救出活動だけでなく、私生活、日々の暮らしにも密着しました。
私たちは、ストレートニュースとして伝えられる情報の裏に隠れていた、彼らの経験、つまり父親、友人、そして救助隊員として直面した恐怖、希望、そして困難な選択を、あますところなく描き出すことを目指しました。このような環境での撮影は、撮影部隊も同じ危険にさらされることを意味しましたが、だからこそ彼らの目を通して、そして街の内側から、彼らの物語を誠実かつ深く伝えることができたのです。
アサド政権時代にシリアを逃れて、イギリスに渡り、亡命を申請されました。難民映画基金の支援を受けた作品は、その経験に関わる内容だとうかがっています。
『アレッポ 最後の男たち』の後、2023年のトルコ・シリア地震を描いたドキュメンタリー映画『Death without Mercy』のプロデューサーを務めました。自分が生きている場所で、何かが起こったとき、その映画を撮ることが自分の責任だと感じていたからです。映画制作者として、というよりも、ある出来事を体験した人間の責任として、ですね。
しかし最終的に、私はイギリスに渡りました。しばらくのあいだ足止めをされ、亡命を申請し、今は故国を離れて難民として生きています。その過程を経験しながら、自分が直面したこと、体験していること、これを記録しなければならない、と考えました。これまでの映画もすべて、自分の身の回りで起きている状況を扱ってきました。私にとってドキュメンタリー映画とは、自分が経験していることをそのままとらえるもの、としてつづいているのです。
ただ、今回の危険はこれまでとは次元が異なります。亡命を求めることは、生命に関わる物理的なリスクではない。しかし、次にいつ、何が起きるのかまったく予測できない状況に宙吊りにされている。そのなかで、自分の生まれ故郷からどうやって逃れてきたのか、逃れなければならなかった理由は何か、この避難のあいだにおおきな意味を持つことになった、大切な友人との友情についても、難民映画基金の支援を受ける次回作で描きたいと考えたのです。未来というものは、過去につながっています。過去が未来を形づくっていく。しかも過去の記録をたどって深く潜ってゆくことには、別の次元の危険がある、とも言えるのです。
▲ 『アレッポ 最後の男たち 2017』 監督:フェラス・ファヤード 共同監督:スティン・ヨハネセン/ホワイト・ヘルメットのメンバーたちが空を見上げ、戦闘機の接近を警戒している様子を捉えたシーン。 配給:ユナイテッドピープル/©Larm Film
難民映画基金による助成は、今度の映画にどのような役割を果たしていますか?
この数年のあいだの難民に対する政策や、受け入れ国側の感情の変化はとてもおおきいと感じています。国家にとって難民や亡命申請者が過大なコストになっていると非難されたり、犯罪者として見なされたり、危険視されたりする場合もあります。政治家の主張の道具として使われることも増えています。
私はどのような問題であれ、理解なしで解決することは不可能だと考えています。私や私のまわりの人々が個人的に体験してきたことを、この難民映画基金のサポートを得て映像化し、難民や亡命申請者の物語を多くの人々に見てもらうことによって、より深い理解がもたらされるはずと信じています。
映画を見ることによって対話が生まれ、変化がもたらされ、すべての人々にとってよりよい世界が築かれていくよう、私にできることをこれからも続けていきます。私にとって、難民映画基金から得たこの機会は、人生の新たな、しかし困難な章の真っ只中に、希望のとびらを開くものでした。経済的にも精神的にも、創作のための空間、自由、そして励ましを与えてくれる、かけがえのない出発点です。
この支援は、単なる資金援助以上の意味を持つ、意義深い連帯の表れだと心から感じています。ケイト・ブランシェット氏、UNHCR、ユニクロ、ヒューバート・バルス基金、そしてこの基金の実現に尽力いただいたすべての方々に深く感謝いたします。
Displacement Film Fund(難民映画基金)とは?
「難民映画基金」は、避難を余儀なくされた映画制作者、または避難民としての経験を描いた実績のある映画制作者の活動を支援し・助成するために設立されました。2025年のロッテルダム国際映画祭(IFFR)において、国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)親善大使であるケイト・ブランシェット氏が発表し、マスターマインド、ユニクロ、オランダの文化支援財団ドローム・エン・ダード、慈善財団のタマーファミリー財団、難民支援NGOのアマホロ連合が創設パートナーとして名を連ねています。ヒューバート・バルス基金を運営パートナー、国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)を戦略パートナーとし、短編映画への助成制度のパイロット版として開始しています。
難民映画基金による第一回の支援を受けることになった5名のうちの1人、シリア出身の映画監督ハサン・カッタンさんは故国のシリア内戦をどのように撮りつづけたのでしょうか。
戦火のもとでつくられたドキュメンタリー映画の現場と、ロンドンで制作中の次作について、お話をうかがいました。
映画監督になるまでの歩みについてお聞かせください。
1992年、シリア北部の都市アレッポに生まれました。ごく普通の家庭で育ちました。子どもの頃は平和な日々で、日本のアニメの「名探偵コナン」や「ポケットモンスター」、「ドラゴンボール」や「ONE PIECE」などを夢中になって見ていました。大学に進んでからは法律を学びました。その頃、自由と民主主義を求める人々の声がシリア国内でおおきくなり、アレッポでも平和的なデモが始まりました。私もその運動に触発され、デモに参加しました。
▲ アレッポ、2016年12月 - 包囲された東アレッポからの家族たちが、6か月に及ぶ包囲の後に締結された避難合意に基づき、ラモーセ交差点で待機している様子。数千の家族が、過酷な人道状況の中、何時間も地面に座って「緑のバス」や赤新月社およびICRC(国際赤十字)の車列による市外への避難を待っていた。ⒸAMC(Hasan Kattan - Aleppo Media Center)
デモが拡大し、2011年にシリアでの蜂起が始まったとき、私はスマートフォン1つで、目にしたものを撮影し始めたのです。何が起きているのかを記録し、外の世界へ伝える義務を感じたからです。市民ジャーナリストやメディア関係者の仲間が集まって設立した、「アレッポ・メディア・センター」の共同設立者の1人になりました。戦争犯罪や軍隊に包囲された都市での日々の現実を記録し、報道することが、自分の仕事になっていったのです。私たちにとって、ここでの物語を伝えることは単に生きていくためではなく、抵抗そのものでした。
▲ 『We Will Return My Love』 アレッポ、2016年12月 - 包囲下で結婚し、その後故郷を離れざるを得なかったカップルのラブストーリーを描いた短編映画の主人公、サーレハとマルワ。写真は、爆撃と包囲の後、避難のための「緑のバス」が到着するのを待っている間に撮影されたもの。ⒸAMC(Saleh Hasnawi - Aleppo Media Center)
報道の仕事からドキュメンタリー映画の制作へと向かったのはなぜでしょうか。
私はニュース編集者や記者という役割で、BBCやChannel 4、アルジャジーラ・イングリッシュ、その他の国際NGOとも仕事を重ねてきました。報道の仕事をつづけるのが何より大切でした。
アサド政権とそれを支援する同盟者が、プロパガンダや偽情報をさかんに流すことによって、人々のほんとうの物語が歪められ、消し去られる可能性があったからです。こうした偽りの情報に騙されず、真実を守り、保存して、伝えていくという報道の使命を信じて、十年あまり活動してきたのです。
▲ ハナーノの民間防衛センター(アレッポ、2016年) - 映画『アレッポ 最後の男たち』の撮影中に撮影された写真。ホワイト・ヘルメットのボランティアが空を見上げ、住宅街に樽爆弾を投下しようとしているヘリコプターを追跡している様子が写されている。この瞬間を、ハサンさん(写真左)は脅威を感じながら観察・報告しながら記録していた。ⒸAMC(Thaer ِAlHalabi - Aleppo Media Center)
最初のうちは、映画作家になるつもりはありませんでした。ただ、圧倒的な困難や不正義、目の前で起きている、語られないままの人間の物語に接するうちに、自分がいま目撃し、見聞きしているものを、もっと深く取材し、撮影して、広く伝えていかなければならないと思うようになりました。ここにいない人をも動かすような物語になりうるのは、ドキュメンタリー映画ではないか、と気づいたのです。
大きな話題となり、さまざまな賞を受けることになったドキュメンタリー映画『ホワイト・ヘルメット』(2016年 アカデミー賞短編ドキュメンタリー映画賞受賞)について話を聞かせてください。どのような立場でこの映画に関わりましたか?
『ホワイト・ヘルメット』の撮影は、私にとって職業的にも個人的にも、大きな転機となりました。私はアレッポ・メディア・センターのチームの一員として、シリア国内で撮影監督を務めました。「ホワイト・ヘルメット」の隊員は、アレッポの街で爆撃を受けた現場に駆けつけ、最も危険な瞬間に、瓦礫の下に生き埋めになった人々を救い出すボランティアとして活動する、ごく普通の人々です。彼らはしばしば、次につづく爆撃の脅威にさらされていました。
この活動を記録することは、何よりも危険で感情を揺さぶられる状況の彼らとともに活動をするということと同義でした。私たちは彼らとともに救急車に乗り、爆撃現場に入り、捜索救助の痛ましくも果敢な瞬間を捉えました。彼らが救助した人々は、多くの場合、すでに命を落としていました。しかし、そのような喪失の瞬間においても、彼らの人間性、勇気、そしてどんな犠牲を払っても他者を救おうとする信念を目の当たりにすることは、計り知れない力となりました。
私たちの使命は、彼らの日々の生活を誠実に記録し、何が起こっているのかという真実を伝えることでした。彼らに寄り添うことで、私は変わりました。それはただ事実を写し取るのではなく、彼らの声と犠牲を世界に伝えることでした。
『アレッポ 最後の男たち』(2017年 アカデミー賞長編ドキュメンタリー部門ノミネート作品。サンダンス映画祭ワールド・シネマドキュメンタリー・コンペティション部門グランプリなど世界中で23の映画賞を受賞)には、どのように関わられましたか?
▲ 『アレッポ 最後の男たち 2017』 監督:フェラス・ファヤード 共同監督:スティン・ヨハネセン 第90回アカデミー賞長編ドキュメンタリー部門ノミネート作品。2017年サンダンス映画祭ワールド・シネマ ドキュメンタリー・コンペティション部門グランプリ。ほか、世界中で23の映画賞を受賞した。配給:ユナイテッドピープル/©Larm Film
『アレッポ 最後の男たち』では、私はディレクターチームの一員で、撮影監督も務めました。2年以上にわたり、アレッポのホワイト・ヘルメットの隊員たちと活動をともにしました。撮影では救出活動だけでなく、私生活、日々の暮らしにも密着しました。
私たちは、ストレートニュースとして伝えられる情報の裏に隠れていた、彼らの経験、つまり父親、友人、そして救助隊員として直面した恐怖、希望、そして困難な選択を、あますところなく描き出すことを目指しました。このような環境での撮影は、撮影部隊も同じ危険にさらされることを意味しましたが、だからこそ彼らの目を通して、そして街の内側から、彼らの物語を誠実かつ深く伝えることができたのです。
アサド政権時代にシリアを逃れて、イギリスに渡り、亡命を申請されました。難民映画基金の支援を受けた作品は、その経験に関わる内容だとうかがっています。
『アレッポ 最後の男たち』の後、2023年のトルコ・シリア地震を描いたドキュメンタリー映画『Death without Mercy』のプロデューサーを務めました。自分が生きている場所で、何かが起こったとき、その映画を撮ることが自分の責任だと感じていたからです。映画制作者として、というよりも、ある出来事を体験した人間の責任として、ですね。
しかし最終的に、私はイギリスに渡りました。しばらくのあいだ足止めをされ、亡命を申請し、今は故国を離れて難民として生きています。その過程を経験しながら、自分が直面したこと、体験していること、これを記録しなければならない、と考えました。これまでの映画もすべて、自分の身の回りで起きている状況を扱ってきました。私にとってドキュメンタリー映画とは、自分が経験していることをそのままとらえるもの、としてつづいているのです。
ただ、今回の危険はこれまでとは次元が異なります。亡命を求めることは、生命に関わる物理的なリスクではない。しかし、次にいつ、何が起きるのかまったく予測できない状況に宙吊りにされている。そのなかで、自分の生まれ故郷からどうやって逃れてきたのか、逃れなければならなかった理由は何か、この避難のあいだにおおきな意味を持つことになった、大切な友人との友情についても、難民映画基金の支援を受ける次回作で描きたいと考えたのです。未来というものは、過去につながっています。過去が未来を形づくっていく。しかも過去の記録をたどって深く潜ってゆくことには、別の次元の危険がある、とも言えるのです。
▲ 『アレッポ 最後の男たち 2017』 監督:フェラス・ファヤード 共同監督:スティン・ヨハネセン/ホワイト・ヘルメットのメンバーたちが空を見上げ、戦闘機の接近を警戒している様子を捉えたシーン。 配給:ユナイテッドピープル/©Larm Film
難民映画基金による助成は、今度の映画にどのような役割を果たしていますか?
この数年のあいだの難民に対する政策や、受け入れ国側の感情の変化はとてもおおきいと感じています。国家にとって難民や亡命申請者が過大なコストになっていると非難されたり、犯罪者として見なされたり、危険視されたりする場合もあります。政治家の主張の道具として使われることも増えています。
私はどのような問題であれ、理解なしで解決することは不可能だと考えています。私や私のまわりの人々が個人的に体験してきたことを、この難民映画基金のサポートを得て映像化し、難民や亡命申請者の物語を多くの人々に見てもらうことによって、より深い理解がもたらされるはずと信じています。
映画を見ることによって対話が生まれ、変化がもたらされ、すべての人々にとってよりよい世界が築かれていくよう、私にできることをこれからも続けていきます。私にとって、難民映画基金から得たこの機会は、人生の新たな、しかし困難な章の真っ只中に、希望のとびらを開くものでした。経済的にも精神的にも、創作のための空間、自由、そして励ましを与えてくれる、かけがえのない出発点です。
この支援は、単なる資金援助以上の意味を持つ、意義深い連帯の表れだと心から感じています。ケイト・ブランシェット氏、UNHCR、ユニクロ、ヒューバート・バルス基金、そしてこの基金の実現に尽力いただいたすべての方々に深く感謝いたします。
Displacement Film Fund(難民映画基金)とは?
「難民映画基金」は、避難を余儀なくされた映画制作者、または避難民としての経験を描いた実績のある映画制作者の活動を支援し・助成するために設立されました。2025年のロッテルダム国際映画祭(IFFR)において、国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)親善大使であるケイト・ブランシェット氏が発表し、マスターマインド、ユニクロ、オランダの文化支援財団ドローム・エン・ダード、慈善財団のタマーファミリー財団、難民支援NGOのアマホロ連合が創設パートナーとして名を連ねています。ヒューバート・バルス基金を運営パートナー、国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)を戦略パートナーとし、短編映画への助成制度のパイロット版として開始しています。
ユニクロは、難民や避難を経験した映画制作者、または避難民としての経験を描いた実績のある映画制作者の作品制作を支援する「難民映画基金(Displacement Film Fund)」をサポートしています。創設パートナーとして、ユニクロは10万ユーロを寄付し、彼らの物語にスポットライトをあて、難民や避難民への理解を深める活動を後押ししていきます。
難民映画基金による第一回の支援を受けることになった5名のうちの1人、シリア出身の映画監督ハサン・カッタンさんは故国のシリア内戦をどのように撮りつづけたのでしょうか。
戦火のもとでつくられたドキュメンタリー映画の現場と、ロンドンで制作中の次作について、お話をうかがいました。
映画監督になるまでの歩みについてお聞かせください。
1992年、シリア北部の都市アレッポに生まれました。ごく普通の家庭で育ちました。子どもの頃は平和な日々で、日本のアニメの「名探偵コナン」や「ポケットモンスター」、「ドラゴンボール」や「ONE PIECE」などを夢中になって見ていました。大学に進んでからは法律を学びました。その頃、自由と民主主義を求める人々の声がシリア国内でおおきくなり、アレッポでも平和的なデモが始まりました。私もその運動に触発され、デモに参加しました。
▲ アレッポ、2016年12月 - 包囲された東アレッポからの家族たちが、6か月に及ぶ包囲の後に締結された避難合意に基づき、ラモーセ交差点で待機している様子。数千の家族が、過酷な人道状況の中、何時間も地面に座って「緑のバス」や赤新月社およびICRC(国際赤十字)の車列による市外への避難を待っていた。ⒸAMC(Hasan Kattan - Aleppo Media Center)
デモが拡大し、2011年にシリアでの蜂起が始まったとき、私はスマートフォン1つで、目にしたものを撮影し始めたのです。何が起きているのかを記録し、外の世界へ伝える義務を感じたからです。市民ジャーナリストやメディア関係者の仲間が集まって設立した、「アレッポ・メディア・センター」の共同設立者の1人になりました。戦争犯罪や軍隊に包囲された都市での日々の現実を記録し、報道することが、自分の仕事になっていったのです。私たちにとって、ここでの物語を伝えることは単に生きていくためではなく、抵抗そのものでした。
▲ 『We Will Return My Love』 アレッポ、2016年12月 - 包囲下で結婚し、その後故郷を離れざるを得なかったカップルのラブストーリーを描いた短編映画の主人公、サーレハとマルワ。写真は、爆撃と包囲の後、避難のための「緑のバス」が到着するのを待っている間に撮影されたもの。ⒸAMC(Saleh Hasnawi - Aleppo Media Center)
報道の仕事からドキュメンタリー映画の制作へと向かったのはなぜでしょうか。
私はニュース編集者や記者という役割で、BBCやChannel 4、アルジャジーラ・イングリッシュ、その他の国際NGOとも仕事を重ねてきました。報道の仕事をつづけるのが何より大切でした。
アサド政権とそれを支援する同盟者が、プロパガンダや偽情報をさかんに流すことによって、人々のほんとうの物語が歪められ、消し去られる可能性があったからです。こうした偽りの情報に騙されず、真実を守り、保存して、伝えていくという報道の使命を信じて、十年あまり活動してきたのです。
▲ ハナーノの民間防衛センター(アレッポ、2016年) - 映画『アレッポ 最後の男たち』の撮影中に撮影された写真。ホワイト・ヘルメットのボランティアが空を見上げ、住宅街に樽爆弾を投下しようとしているヘリコプターを追跡している様子が写されている。この瞬間を、ハサンさん(写真左)は脅威を感じながら観察・報告しながら記録していた。ⒸAMC(Thaer ِAlHalabi - Aleppo Media Center)
最初のうちは、映画作家になるつもりはありませんでした。ただ、圧倒的な困難や不正義、目の前で起きている、語られないままの人間の物語に接するうちに、自分がいま目撃し、見聞きしているものを、もっと深く取材し、撮影して、広く伝えていかなければならないと思うようになりました。ここにいない人をも動かすような物語になりうるのは、ドキュメンタリー映画ではないか、と気づいたのです。
大きな話題となり、さまざまな賞を受けることになったドキュメンタリー映画『ホワイト・ヘルメット』(2016年 アカデミー賞短編ドキュメンタリー映画賞受賞)について話を聞かせてください。どのような立場でこの映画に関わりましたか?
『ホワイト・ヘルメット』の撮影は、私にとって職業的にも個人的にも、大きな転機となりました。私はアレッポ・メディア・センターのチームの一員として、シリア国内で撮影監督を務めました。「ホワイト・ヘルメット」の隊員は、アレッポの街で爆撃を受けた現場に駆けつけ、最も危険な瞬間に、瓦礫の下に生き埋めになった人々を救い出すボランティアとして活動する、ごく普通の人々です。彼らはしばしば、次につづく爆撃の脅威にさらされていました。
この活動を記録することは、何よりも危険で感情を揺さぶられる状況の彼らとともに活動をするということと同義でした。私たちは彼らとともに救急車に乗り、爆撃現場に入り、捜索救助の痛ましくも果敢な瞬間を捉えました。彼らが救助した人々は、多くの場合、すでに命を落としていました。しかし、そのような喪失の瞬間においても、彼らの人間性、勇気、そしてどんな犠牲を払っても他者を救おうとする信念を目の当たりにすることは、計り知れない力となりました。
私たちの使命は、彼らの日々の生活を誠実に記録し、何が起こっているのかという真実を伝えることでした。彼らに寄り添うことで、私は変わりました。それはただ事実を写し取るのではなく、彼らの声と犠牲を世界に伝えることでした。
『アレッポ 最後の男たち』(2017年 アカデミー賞長編ドキュメンタリー部門ノミネート作品。サンダンス映画祭ワールド・シネマドキュメンタリー・コンペティション部門グランプリなど世界中で23の映画賞を受賞)には、どのように関わられましたか?
▲ 『アレッポ 最後の男たち 2017』 監督:フェラス・ファヤード 共同監督:スティン・ヨハネセン 第90回アカデミー賞長編ドキュメンタリー部門ノミネート作品。2017年サンダンス映画祭ワールド・シネマ ドキュメンタリー・コンペティション部門グランプリ。ほか、世界中で23の映画賞を受賞した。配給:ユナイテッドピープル/©Larm Film
『アレッポ 最後の男たち』では、私はディレクターチームの一員で、撮影監督も務めました。2年以上にわたり、アレッポのホワイト・ヘルメットの隊員たちと活動をともにしました。撮影では救出活動だけでなく、私生活、日々の暮らしにも密着しました。
私たちは、ストレートニュースとして伝えられる情報の裏に隠れていた、彼らの経験、つまり父親、友人、そして救助隊員として直面した恐怖、希望、そして困難な選択を、あますところなく描き出すことを目指しました。このような環境での撮影は、撮影部隊も同じ危険にさらされることを意味しましたが、だからこそ彼らの目を通して、そして街の内側から、彼らの物語を誠実かつ深く伝えることができたのです。
アサド政権時代にシリアを逃れて、イギリスに渡り、亡命を申請されました。難民映画基金の支援を受けた作品は、その経験に関わる内容だとうかがっています。
『アレッポ 最後の男たち』の後、2023年のトルコ・シリア地震を描いたドキュメンタリー映画『Death without Mercy』のプロデューサーを務めました。自分が生きている場所で、何かが起こったとき、その映画を撮ることが自分の責任だと感じていたからです。映画制作者として、というよりも、ある出来事を体験した人間の責任として、ですね。
しかし最終的に、私はイギリスに渡りました。しばらくのあいだ足止めをされ、亡命を申請し、今は故国を離れて難民として生きています。その過程を経験しながら、自分が直面したこと、体験していること、これを記録しなければならない、と考えました。これまでの映画もすべて、自分の身の回りで起きている状況を扱ってきました。私にとってドキュメンタリー映画とは、自分が経験していることをそのままとらえるもの、としてつづいているのです。
ただ、今回の危険はこれまでとは次元が異なります。亡命を求めることは、生命に関わる物理的なリスクではない。しかし、次にいつ、何が起きるのかまったく予測できない状況に宙吊りにされている。そのなかで、自分の生まれ故郷からどうやって逃れてきたのか、逃れなければならなかった理由は何か、この避難のあいだにおおきな意味を持つことになった、大切な友人との友情についても、難民映画基金の支援を受ける次回作で描きたいと考えたのです。未来というものは、過去につながっています。過去が未来を形づくっていく。しかも過去の記録をたどって深く潜ってゆくことには、別の次元の危険がある、とも言えるのです。
▲ 『アレッポ 最後の男たち 2017』 監督:フェラス・ファヤード 共同監督:スティン・ヨハネセン/ホワイト・ヘルメットのメンバーたちが空を見上げ、戦闘機の接近を警戒している様子を捉えたシーン。 配給:ユナイテッドピープル/©Larm Film
難民映画基金による助成は、今度の映画にどのような役割を果たしていますか?
この数年のあいだの難民に対する政策や、受け入れ国側の感情の変化はとてもおおきいと感じています。国家にとって難民や亡命申請者が過大なコストになっていると非難されたり、犯罪者として見なされたり、危険視されたりする場合もあります。政治家の主張の道具として使われることも増えています。
私はどのような問題であれ、理解なしで解決することは不可能だと考えています。私や私のまわりの人々が個人的に体験してきたことを、この難民映画基金のサポートを得て映像化し、難民や亡命申請者の物語を多くの人々に見てもらうことによって、より深い理解がもたらされるはずと信じています。
映画を見ることによって対話が生まれ、変化がもたらされ、すべての人々にとってよりよい世界が築かれていくよう、私にできることをこれからも続けていきます。私にとって、難民映画基金から得たこの機会は、人生の新たな、しかし困難な章の真っ只中に、希望のとびらを開くものでした。経済的にも精神的にも、創作のための空間、自由、そして励ましを与えてくれる、かけがえのない出発点です。
この支援は、単なる資金援助以上の意味を持つ、意義深い連帯の表れだと心から感じています。ケイト・ブランシェット氏、UNHCR、ユニクロ、ヒューバート・バルス基金、そしてこの基金の実現に尽力いただいたすべての方々に深く感謝いたします。
Displacement Film Fund(難民映画基金)とは?
「難民映画基金」は、避難を余儀なくされた映画制作者、または避難民としての経験を描いた実績のある映画制作者の活動を支援し・助成するために設立されました。2025年のロッテルダム国際映画祭(IFFR)において、国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)親善大使であるケイト・ブランシェット氏が発表し、マスターマインド、ユニクロ、オランダの文化支援財団ドローム・エン・ダード、慈善財団のタマーファミリー財団、難民支援NGOのアマホロ連合が創設パートナーとして名を連ねています。ヒューバート・バルス基金を運営パートナー、国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)を戦略パートナーとし、短編映画への助成制度のパイロット版として開始しています。
難民映画基金による第一回の支援を受けることになった5名のうちの1人、シリア出身の映画監督ハサン・カッタンさんは故国のシリア内戦をどのように撮りつづけたのでしょうか。
戦火のもとでつくられたドキュメンタリー映画の現場と、ロンドンで制作中の次作について、お話をうかがいました。
映画監督になるまでの歩みについてお聞かせください。
1992年、シリア北部の都市アレッポに生まれました。ごく普通の家庭で育ちました。子どもの頃は平和な日々で、日本のアニメの「名探偵コナン」や「ポケットモンスター」、「ドラゴンボール」や「ONE PIECE」などを夢中になって見ていました。大学に進んでからは法律を学びました。その頃、自由と民主主義を求める人々の声がシリア国内でおおきくなり、アレッポでも平和的なデモが始まりました。私もその運動に触発され、デモに参加しました。
▲ アレッポ、2016年12月 - 包囲された東アレッポからの家族たちが、6か月に及ぶ包囲の後に締結された避難合意に基づき、ラモーセ交差点で待機している様子。数千の家族が、過酷な人道状況の中、何時間も地面に座って「緑のバス」や赤新月社およびICRC(国際赤十字)の車列による市外への避難を待っていた。ⒸAMC(Hasan Kattan - Aleppo Media Center)
デモが拡大し、2011年にシリアでの蜂起が始まったとき、私はスマートフォン1つで、目にしたものを撮影し始めたのです。何が起きているのかを記録し、外の世界へ伝える義務を感じたからです。市民ジャーナリストやメディア関係者の仲間が集まって設立した、「アレッポ・メディア・センター」の共同設立者の1人になりました。戦争犯罪や軍隊に包囲された都市での日々の現実を記録し、報道することが、自分の仕事になっていったのです。私たちにとって、ここでの物語を伝えることは単に生きていくためではなく、抵抗そのものでした。
▲ 『We Will Return My Love』 アレッポ、2016年12月 - 包囲下で結婚し、その後故郷を離れざるを得なかったカップルのラブストーリーを描いた短編映画の主人公、サーレハとマルワ。写真は、爆撃と包囲の後、避難のための「緑のバス」が到着するのを待っている間に撮影されたもの。ⒸAMC(Saleh Hasnawi - Aleppo Media Center)
報道の仕事からドキュメンタリー映画の制作へと向かったのはなぜでしょうか。
私はニュース編集者や記者という役割で、BBCやChannel 4、アルジャジーラ・イングリッシュ、その他の国際NGOとも仕事を重ねてきました。報道の仕事をつづけるのが何より大切でした。
アサド政権とそれを支援する同盟者が、プロパガンダや偽情報をさかんに流すことによって、人々のほんとうの物語が歪められ、消し去られる可能性があったからです。こうした偽りの情報に騙されず、真実を守り、保存して、伝えていくという報道の使命を信じて、十年あまり活動してきたのです。
▲ ハナーノの民間防衛センター(アレッポ、2016年) - 映画『アレッポ 最後の男たち』の撮影中に撮影された写真。ホワイト・ヘルメットのボランティアが空を見上げ、住宅街に樽爆弾を投下しようとしているヘリコプターを追跡している様子が写されている。この瞬間を、ハサンさん(写真左)は脅威を感じながら観察・報告しながら記録していた。ⒸAMC(Thaer ِAlHalabi - Aleppo Media Center)
最初のうちは、映画作家になるつもりはありませんでした。ただ、圧倒的な困難や不正義、目の前で起きている、語られないままの人間の物語に接するうちに、自分がいま目撃し、見聞きしているものを、もっと深く取材し、撮影して、広く伝えていかなければならないと思うようになりました。ここにいない人をも動かすような物語になりうるのは、ドキュメンタリー映画ではないか、と気づいたのです。
大きな話題となり、さまざまな賞を受けることになったドキュメンタリー映画『ホワイト・ヘルメット』(2016年 アカデミー賞短編ドキュメンタリー映画賞受賞)について話を聞かせてください。どのような立場でこの映画に関わりましたか?
『ホワイト・ヘルメット』の撮影は、私にとって職業的にも個人的にも、大きな転機となりました。私はアレッポ・メディア・センターのチームの一員として、シリア国内で撮影監督を務めました。「ホワイト・ヘルメット」の隊員は、アレッポの街で爆撃を受けた現場に駆けつけ、最も危険な瞬間に、瓦礫の下に生き埋めになった人々を救い出すボランティアとして活動する、ごく普通の人々です。彼らはしばしば、次につづく爆撃の脅威にさらされていました。
この活動を記録することは、何よりも危険で感情を揺さぶられる状況の彼らとともに活動をするということと同義でした。私たちは彼らとともに救急車に乗り、爆撃現場に入り、捜索救助の痛ましくも果敢な瞬間を捉えました。彼らが救助した人々は、多くの場合、すでに命を落としていました。しかし、そのような喪失の瞬間においても、彼らの人間性、勇気、そしてどんな犠牲を払っても他者を救おうとする信念を目の当たりにすることは、計り知れない力となりました。
私たちの使命は、彼らの日々の生活を誠実に記録し、何が起こっているのかという真実を伝えることでした。彼らに寄り添うことで、私は変わりました。それはただ事実を写し取るのではなく、彼らの声と犠牲を世界に伝えることでした。
『アレッポ 最後の男たち』(2017年 アカデミー賞長編ドキュメンタリー部門ノミネート作品。サンダンス映画祭ワールド・シネマドキュメンタリー・コンペティション部門グランプリなど世界中で23の映画賞を受賞)には、どのように関わられましたか?
▲ 『アレッポ 最後の男たち 2017』 監督:フェラス・ファヤード 共同監督:スティン・ヨハネセン 第90回アカデミー賞長編ドキュメンタリー部門ノミネート作品。2017年サンダンス映画祭ワールド・シネマ ドキュメンタリー・コンペティション部門グランプリ。ほか、世界中で23の映画賞を受賞した。配給:ユナイテッドピープル/©Larm Film
『アレッポ 最後の男たち』では、私はディレクターチームの一員で、撮影監督も務めました。2年以上にわたり、アレッポのホワイト・ヘルメットの隊員たちと活動をともにしました。撮影では救出活動だけでなく、私生活、日々の暮らしにも密着しました。
私たちは、ストレートニュースとして伝えられる情報の裏に隠れていた、彼らの経験、つまり父親、友人、そして救助隊員として直面した恐怖、希望、そして困難な選択を、あますところなく描き出すことを目指しました。このような環境での撮影は、撮影部隊も同じ危険にさらされることを意味しましたが、だからこそ彼らの目を通して、そして街の内側から、彼らの物語を誠実かつ深く伝えることができたのです。
アサド政権時代にシリアを逃れて、イギリスに渡り、亡命を申請されました。難民映画基金の支援を受けた作品は、その経験に関わる内容だとうかがっています。
『アレッポ 最後の男たち』の後、2023年のトルコ・シリア地震を描いたドキュメンタリー映画『Death without Mercy』のプロデューサーを務めました。自分が生きている場所で、何かが起こったとき、その映画を撮ることが自分の責任だと感じていたからです。映画制作者として、というよりも、ある出来事を体験した人間の責任として、ですね。
しかし最終的に、私はイギリスに渡りました。しばらくのあいだ足止めをされ、亡命を申請し、今は故国を離れて難民として生きています。その過程を経験しながら、自分が直面したこと、体験していること、これを記録しなければならない、と考えました。これまでの映画もすべて、自分の身の回りで起きている状況を扱ってきました。私にとってドキュメンタリー映画とは、自分が経験していることをそのままとらえるもの、としてつづいているのです。
ただ、今回の危険はこれまでとは次元が異なります。亡命を求めることは、生命に関わる物理的なリスクではない。しかし、次にいつ、何が起きるのかまったく予測できない状況に宙吊りにされている。そのなかで、自分の生まれ故郷からどうやって逃れてきたのか、逃れなければならなかった理由は何か、この避難のあいだにおおきな意味を持つことになった、大切な友人との友情についても、難民映画基金の支援を受ける次回作で描きたいと考えたのです。未来というものは、過去につながっています。過去が未来を形づくっていく。しかも過去の記録をたどって深く潜ってゆくことには、別の次元の危険がある、とも言えるのです。
▲ 『アレッポ 最後の男たち 2017』 監督:フェラス・ファヤード 共同監督:スティン・ヨハネセン/ホワイト・ヘルメットのメンバーたちが空を見上げ、戦闘機の接近を警戒している様子を捉えたシーン。 配給:ユナイテッドピープル/©Larm Film
難民映画基金による助成は、今度の映画にどのような役割を果たしていますか?
この数年のあいだの難民に対する政策や、受け入れ国側の感情の変化はとてもおおきいと感じています。国家にとって難民や亡命申請者が過大なコストになっていると非難されたり、犯罪者として見なされたり、危険視されたりする場合もあります。政治家の主張の道具として使われることも増えています。
私はどのような問題であれ、理解なしで解決することは不可能だと考えています。私や私のまわりの人々が個人的に体験してきたことを、この難民映画基金のサポートを得て映像化し、難民や亡命申請者の物語を多くの人々に見てもらうことによって、より深い理解がもたらされるはずと信じています。
映画を見ることによって対話が生まれ、変化がもたらされ、すべての人々にとってよりよい世界が築かれていくよう、私にできることをこれからも続けていきます。私にとって、難民映画基金から得たこの機会は、人生の新たな、しかし困難な章の真っ只中に、希望のとびらを開くものでした。経済的にも精神的にも、創作のための空間、自由、そして励ましを与えてくれる、かけがえのない出発点です。
この支援は、単なる資金援助以上の意味を持つ、意義深い連帯の表れだと心から感じています。ケイト・ブランシェット氏、UNHCR、ユニクロ、ヒューバート・バルス基金、そしてこの基金の実現に尽力いただいたすべての方々に深く感謝いたします。
Displacement Film Fund(難民映画基金)とは?
「難民映画基金」は、避難を余儀なくされた映画制作者、または避難民としての経験を描いた実績のある映画制作者の活動を支援し・助成するために設立されました。2025年のロッテルダム国際映画祭(IFFR)において、国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)親善大使であるケイト・ブランシェット氏が発表し、マスターマインド、ユニクロ、オランダの文化支援財団ドローム・エン・ダード、慈善財団のタマーファミリー財団、難民支援NGOのアマホロ連合が創設パートナーとして名を連ねています。ヒューバート・バルス基金を運営パートナー、国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)を戦略パートナーとし、短編映画への助成制度のパイロット版として開始しています。
デイリーアクセスランキング
もっと見る話題のワード
UNIQLO Co. Ltd. published this content on December 19, 2025, and is solely responsible for the information contained herein. Distributed via Public Technologies (PUBT), unedited and unaltered, on December 21, 2025 at 01:07 UTC. If you believe the information included in the content is inaccurate or outdated and requires editing or removal, please contact us at [email protected]